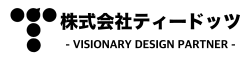昨今の保育園の開所が急増したこともあって、保育士の獲得が非常に難しくなってきました。
これは、保育園業界だけではなく、サービス業、中小企業の多くが直面している問題です。
昔はハローワークから応募があったのに、最近は全くない。
・求人サイトへの広告
・紹介業への依頼
・派遣の依頼
で人材をなんとか確保している。
急な欠員を高額だったけどどうしようもなくて、紹介会社から紹介してもらってなんとかしのいだ!!ということも少なくないのではないでしょうか?
さらに、近年の収支を見ると、保育士の確保のための広告費の支出が爆上がりし、収支バランスを崩す大きな要因になっている施設も少なくなく、収入がある程度決まってしまっている保育業界においては、広告費の支出増は、施設運営として致命的な支出になりかねません。
もちろんこれは保育園業界のみならず、中小企業でも、広告を打ち続けているものの、良い人材、採用までになかなか至らない。だから広告を出し続けなくてはならず、健全な経営をする上では非常に重い支出負担となります。
では、今回は保育士の人手不足を解消するにはどうしたら良いかを考えてみます。
人材については、何かをすればすぐ解決する。ということにはなりませんよね。
働いている皆さんの理解や協力がなければいけないし、新入・途中入社に限らず職員育成には時間もかかります。
なので、これをやれば良いと即時的解決策を伝えることはできないのですが、次の視点で対策を考えるのは良いと思います。
・短期的な対策:シフトの見直し、無資格者の雇用
・中長期的な対策:定着率の向上
シフトを作るのは本当に大変ですよね。
保育の合間に時間を見つけて、なんとか毎月作成している。と、大変苦労されている先生も多いのではないでしょうか。
私もシフトを作っていた時は、本当に気が重くなりました。
作るのは大変でしたが、そのシフトを分析して若干の工夫をしてみることで、配置が改善することにも気づきました。
クライエント様からシフトを見て欲しいとのことで拝見した時、
・考え方を変えてみる。
・やり方を変えてみる。
・工夫してみる。
という視点からシフトを見直し方を助言してみると、
人が増えてはいないのに、日々の保育の人手不足感がかなり和らいだ。というご感想をいただきます。
先生方と話をしていくうちに分かってきたこととしては、シフト作成者はシフトの作成方法について学んだことがなく独自に作成している先生が少なくない。ということでした。
外部からのアドバイスによって気づきが得られることで、まるでパズルが上手くハマるような印象です。
シフトの工夫以外については、
保育士又は幼稚園教諭の有資格者ではない人材を採用し、その採用した人材を適材適所に配置する。ということも考えていきます。
保育現場では、保育士や幼稚園教諭が全てのことをやる。と思っている方も少なくないようで、
有資格者でないと、そもそも何の仕事をお願いして良いのかわからない。と伺います。
ここでは意識改革が必要なのですが、有資格者ではない人材こそできることや、してもらいたいことを業務に落とし込み、それをお願いする。
これにより有資格者の負担が軽減され、保育に集中する環境が少しでも改善できる。ということができます。
有資格者ではない人材を雇っているがそう上手くいかない。
言っている事は理解できるけど、どうしたら良いかわからない。
ということであればぜひご相談ください。
中長期的な対策としては、定着率の向上です。
定着率の向上は永遠のテーマであります。
退職理由に「給与が低い。」というのはよく聞く話ですが、定着率向上には、別の要因があることも再認識しておきたいところです。
令和4年度東京都保育士実態調査によると、職場選択時と退職理由の一部を抜粋すると次のとおりです。
・勤務地(自宅から近い等) 72.3%
・職場の人間関係 51.9%
・給与が高いこと 38.5%
・休暇が多い・とりやすい 36.9%
・勤務時間・交代制の融通がきく 36.5%
・保育理念への共感 35.9%
などがあります。
一方、退職理由は次のとおりです。
・職場の人間関係 31.5%
・仕事量が多い 23.1%
・給与が安い 22.1%
・健康上の理由(体力含む) 20.6%
・労働時間が長い 18.6%
「職場の人間関係」が「仕事量が多い。」というのが主な退職理由の1つになります。
「人間関係」と「業務量」という言葉にはいろいろな要因が含まれています。
先生によって仕事の内容を深掘りすると、それぞれの立場や経験値の違いもあって、若干違っているということはよくあります。
この課題へ取り組み解決するには、原因を1つ1つ紐どいて、対応をしていかなくてはなりません。
「人間関係」については、
コミュニケーションなどのコラムで触れていますので、ご興味がありましたらお読みください。
「業務量が多い」については、
例えば、業務内容について座学研修(OFFJT)などで教えられずに現場で学んでいく(OJT)ということが多いため、
・職員同士で無駄な動きがあると感じる。
・これであっているのか?など不安なままに仕事をしている。
などという話も伺います。
人手不足だから仕方ない。というのが現実なところですが、ベテラン、新人に関係なく、職員が役割と業務を理解しているがしっかりしている施設は、不満による退職者は少ない傾向にあると感じています。
業務改善をしたいが何から手をつけたら良いかわからない。
業務理解、役割理解について必要性を感じている。
職員に伝えていきたいのでやり方を知りたい。
など、
改善方法や仕組みづくりについてご相談や、鳥飼のコンサルティングにご興味がございましたらお気軽にお問い合わせください。
園長経験者によるワンストップコンサルティングなら | 株式会社ティードッツ