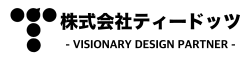埼玉県川越市に本社を持つ、ぎょうざの満州 池野谷ひろみ 代表取締役社長の、いくつかの逆境に立たされながらも、無事に乗り越えてきたエピソードを拝見し、逆境の乗り越えかたについて書いてみたいと思います。
・過去冷夏による米不足や野菜の値段の高騰による原価上昇。
・コロナによる営業時間短縮の営業による売上減。
など、想定外の外的要因により逆境に立たされた時に、次のアイディアで逆境を乗り越えてきたようです。
「マニュアル化」という言葉は、いつも現場に受け入れてもらえないキーワードの1つと感じています。
・これまでそんなものなくてもできてた。
・まるで、これまでの自分たちの仕事を否定されているようだと感じる。
・覚えるのが面倒だし、そんなのがなくてもできる。
・私たちをロボットのように管理するのか?
などなど、
「マニュアル化は大切だ。」と伝えると、このような反応をされることが多いと感じています。
池野谷社長は、メニューのレシピをマニュアル化したそうです。
なぜしたのでしょうか?
マニュアル化により、店舗の味のばらつきを抑えようと考えたそうです。
マニュアルで数値化されたことで、店長やそのスタッフによる経験値・感覚による計量ではなく、可視化された基準が生まれ、食品ロスを約7〜8パーセント縮小できるようになったそうです。
前述のマニュアル導入に加え、パソコンのシステムの導入を行なったそうです。
これにより売上管理を行い、売上と原価の両面から実態を可視化され、客観的な分析による管理ができるようになり、原材料費が改善されたようです。
マニュアル化しただけでは機能しないものです。従業員がそのマニュアルを理解して、組織に浸透させて、運用できるようになる必要があります。
つまり、マニュアルで基準を作り、パソコンのシステムなどで分析・管理する。という、サイクルを仕組み化することが大事だということです。
マニュアル化、システム化により、現状の課題や問題を表出させて客観的に認識できるようにすることで、組織として基準が統一され、対策を検討しやすくなります。
しかしそれでも超えられない苦境では何を基準に判断をしていくか?については、どうでしょうか?
池野谷社長によると、
「安全・おいしい・健康、安心なものを提供する。」
その理念に基づいて決断する。
つまり、
理念に立ち返って、やるべきことを判断・実行する。
ということが大切だそうです。
未来を決める決断は誰もが怖いものです。原点に立ち返り、理念に基づいていくことで、信念を貫き、1つ前に進めるのだと教えてくれます。
ティードッツのコンサルティングでは、従業員がやりがいを持って働く組織を醸成することや、主体的な組織を持続させるための運営支援をさせていただいています。
このコラムについてご相談や、鳥飼のコンサルティングにご興味がございましたらお気軽にお問い合わせください。
園長経験者によるワンストップコンサルティングなら | 株式会社ティードッツ