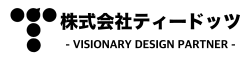アメリカのギャラップ社がまとめた2022年の「熱意ある社員の比率」では、日本は145国中で最低の5%という数字だったそうです。
従業員の働きがいや意欲の低下は商品やサービスの低下を招き、新入社員の定着率(入社3年後)の上昇や従業員の離職率の低下は、働きがいと正の相関関係がある。と、労働白書で示しています。
働きがいを見る上での指標として、ワーク・エンゲージメントという概念があります。
ワーク・エンゲージメントの概念は、2002年にオランダのユトレヒト大学のウィルマー・B・シャウフェリ教授よって提唱されました。
ワーク・エンゲージメントとは、
- 「仕事から活力を得て生き生きとしている(活力)」
- 「仕事に誇りとやりがいを感じている(熱意)」
- 「仕事に熱心に取り組んでいる(没頭)」
の3つが揃った状態。と定義されています。
ワーク・エンゲージメントが高くない企業は、いかに有能な人材を集めることができたとしても、定着することは難しい。と言えます。
さらに、日本でのワーク・エンゲージメントをスコア別に見ていくと、正社員においては、「若い社員」「下位役職者」が低い傾向にあります。
では、ワーク・エンゲージメントをどうやって高めていくのか?
有用な方法としては、次のようなものが挙げられています。
<属性に関係なく全体的に改善しやすい方法>
- 職場の人間関係やコミュニケーションの円滑化
<入社3年後の従業員などに改善しやすい方法>
- 有給休暇の取得促進
- 従業員のキャリア支援(能力開発・自己啓発)

この分析を通してわかることとしては、職場の人間関係とコミュニケーションの円滑になることが、働きがいが向上するうえで有用である。ということです。
具体的な取り組み例としては、
- 1 on 1ミーティングを月1回実施。
- 上司からの積極的な毎日の挨拶。これにによりチームの雰囲気が良くなる。
なども挙げられています。
1 on 1ミーティングにおいては、実施する上司は、面談スキル、コミニュケーションスキルが求められることに注意が必要です。
ようやく採用した従業員に定着してもらうためには、
企業側が従業員のワーク・エンゲージメントを考え、従業員が「働きやすい」と感じ、さらに「働きがい」を感じていける仕組みを作っていきましょう。